めぐるひととせ
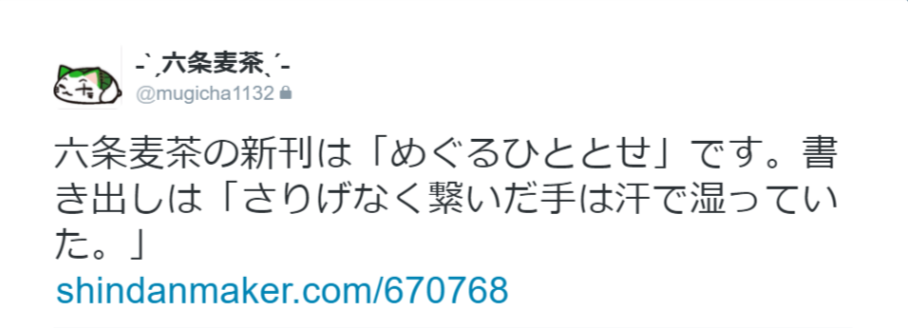
さりげなく繋いだ手は汗で湿っていた。
お前が熱いのだと言い返されるのが常だが、この男の手足はひんやりとしている事が多い。こと、秋から冬の気候に近い海域を走っているときは尚更。
ゾロの故郷であるシモツキ村は、グランドラインと違いちゃんと四季があった。そして、偶然にもと言うべきか、ゾロの誕生日である11月11日、秋とも冬とも言い難い気候と、いまサニー号が走っている新世界の海域の気候が一致している。つまり、日が短く、そこそこに肌寒い。
そんな時のサンジの手足は特に冷えていることが多い。夜なら尚更。それでも、その掌はしっとりとした感触で、そこから熱と緊張を伝えてきた。
クルーがそこそこに増えた今でも、やれ誰それの誕生日だと船長は宴をしたがり、料理人を筆頭に船員は皆それに従ってその日に生まれた人間を祝う。強面で通っているゾロも例外ではなく、幼い船医が飾り付けた紙製のとんがり帽子を被らされたり、プレゼントだと称して狙撃手や船大工から謎のガラクタを貰ったりしてきた。
はじめは宴自体を拒んだが、拒んでも無駄であること、そして自分の誕生日にかこつけて皆騒ぎたいだけだということがわかったことから、ゾロは諦めてそれを受け入れた。
なにより、この日はコックが文句も言わずに酒を飲ませるのだ。自分も痛飲して、陽気に酌すらしてくる。さすがに、これを前に仏頂面を保ちつづけるのは厳しかった。
そんな誕生日の日、ちょうど去年のこの日。
ちょっとした――いや、ゾロと、そしてサンジにしてみれば、大事件が起こった。
酒樽を一人で半分は空けて、酔うとまでは行かずとも少なからずいい気分になったゾロと、前後不覚あと一歩まで行ったサンジが。
事もあろうに、サンジ曰くの「勢いとノリ」だけで、肉体関係を結んでしまったのだ。
翌日、昨日起きたことを覚えているか聞こうとしたゾロは、いつも以上にひどい顔をしたサンジに先手を打たれた。
酒のせいだった、と前置きした上で、彼は言った。
そして、本来であれば今回限りにして、そもそも何もなかったことにしたほうがいいんだろうが。
互いに若い男。そして船には美しい女が二人。
何か間違いがあってはいけないし、発散の手立ては必要かもしれない。
「だから、二人共酒を飲んだとき、そのときに、したい、と互いに思ったなら」
「酒? なんでだ」
「こんな酔狂な真似、文字通り酔って狂わなきゃ出来るわけがねェだろ? 今回だってそうだ。おれもお前も、酔ってた」
サンジはそれ以上の言葉を見つけられなかったようで、ふっと笑った。
ゾロはその時、「なんてな」などととごまかしてなかった事にされるような気がして、素早く返事をした。
「わかった。二人共、酒を飲んで酔ったときだな」
自分から言いだしたはずのサンジは鋭く息を呑んだが、バツの悪い顔をして、まあ当分はねえけどなとゾロから目をそらした。仕方ない。今回の宴で酒は大きく消費した。そして何よりサンジは腰がつらそうだったからだ。
それから、その後。
一年を通して、年が明けたから、冬が明けたから、夏だから、誰それの誕生日だから、花が綺麗だったから、嵐がやんだから――様々な理由で酒を飲み、そして身体を重ねた。
酒を呑むからサンジと肌を合わせるのか、サンジと肌を合わせるために呑んでいるのか。もはやわからなくなるくらいには、回数をこなした。場所は主に格納庫。皆が寝静まったあとに、そこで声を殺して互いを貪った。
サンジの身体も慣れて、交合で快感を得られるようにもなったようで、それは密かな喜びだった。
そして、今日、この日。ゾロの誕生日。
勿論「ある」だろうと思っていたゾロは肩透かしを食らった。せわしなく働いている間、サンジが一滴も酒を飲まなかったからだ。おかげでせっかくの誕生日だと言うのにソワついて、挙句、呑まねえのか、と直球で聞く羽目になった。
サンジは曖昧に笑うだけだった。
そうしていつものように全員が潰れるなり部屋に戻るなりしたあと、ゾロは食器を洗うサンジの後ろ姿を眺めながら不機嫌に酒を飲んでいた。
普段通りであればもうこの時分は、汚れ物だのなんだの全部ほったらかしで、くにゃっとしていてくれなければいけないのに。
今日はこれで終わり、と出された酒がちびちびとしか進まないのは、サンジが食器を洗ったあとに席について飲むんじゃないかと思ったからだ。
けれども、サンジは食器を洗ったあと、エプロンを脱いで、キッチンをあとにしてしまった。汚れたグラスはシンクにおいておけ、と言い残して。
思い返せば、今日は普段の宴のときのように馬鹿みたいに笑ったりすることが少なかったように思う。何かを思い詰めたような。
ちょうど一年前に始まったこの関係。キリが良いから、同じ日に精算してしまおうというつもりなのではないかという可能性にゾロは思い当たった。
だから酒を呑まなかった。ゾロとする気がない、という意思表示。
冗談じゃねえ、と立ち上がり、残り僅かになった酒のボトルをひっつかんでキッチンを出た。
風呂に入っていようがボンクで横になっていようが口に突っ込んで無理やり呑ませてぶち犯してやる、と思った。
特別に名前がつくような関係ではなかったのだとしても、こんな終わり方で納得ができるようなものではなかった。少なくともゾロの中では。
そう思ってサンジの姿を探したが、甲板にも風呂場にも、トレーニングルームにも、アクアリウムバーにも、サンジはいなかった。
まさかと思いながら、格納庫のドアを開ける。
「……酒瓶持ってウロウロすんの、似合いすぎてんな」
「てめェ」
空の樽に腰を掛け、ドアを開けたゾロの姿を見てサンジはそう呑気にコメントした。
この場所。そして手に持った酒。ある種の期待をしてしまいながらそれでもゾロは油断せず険しい顔のままずんずんと歩み寄って、瓶を突き出した。ちゃぷん、と僅かな残りが揺れて音を立てる。
「飲め」
「そりゃお前の為の酒だろ。つーかおれァお前に酒を残すという芸当ができたことに驚きだよ」
誕生日プレゼント、という名目で貰った酒であることは確かだ。
けれど、そんな言葉が聞きたいのではないことを、解っていてはぐらかすようなことを言う。ゾロは額に血管を浮かび上がらせ、酒瓶を乱暴に別の樽の上に置き去りにしてサンジの手首を掴んだ。サンジは振り払おうともせず、されるがままにゾロに床に引き倒される。
どういうつもりだ、と、問い詰めるつもりだった。
けれど、手首を掴んだときに触れた掌の汗、熱、そして伝わる早鐘のような脈。
サンジは緊張している。普段なら少し冷たい指先すら熱く感じるほど。確かめるように掴んだ手を離して、指を絡め合わせる。
抵抗はなかった。指の付け根をギュッと締め付けるように強く掴むと、サンジの長い指がそっと曲がって、ゾロの手の甲をさわりと撫でた。
凶暴な衝動は、いつの間にか消え去っている。だから、ゾロは、かける言葉を変えた。
「いいように、取るぞ」
「良いんじゃねえか?」
ゾロと同じように、心臓がバクバクと高鳴っているくせに、そんな生意気なことを言うので。
ゾロは、初めて、酒を飲んでいない、正気のサンジの唇を塞いだ。
サンジは目を閉じて、軽く唇を噛んでゾロの舌を誘った。酒の味のしないキス。煙草の味がより強く感じられるのに、こっちのほうがよっぽど美味く感じて、舌下からじゅっと涎が出たのがわかった。角度を変えようと一度離すと、ぺろんとサンジに唇の端を舐められて、ついでのように口を開く。
「覚悟しとけよ。一年分溜まってるからな」
「は!? かなりの頻度で抜いてたじゃねェか!」
「おれは最初から酔ってなんざいなかった。お前が覚悟決めるまで待たされた一年分だ」
むむ、とサンジが唇をとがらせる。キスを求められていると好きに解釈して、上下を縫い合わせるように噛み付いてベロベロと口の周りを舐めまわしながら、親指で掌をさわりと撫でると、ビクンとサンジの指先が震えた。元々感じやすいたちだったが、この一年で掌まで立派な性感帯だ。ぐいと引っ張り上げて手のひらの汗まで舐めとると、ニヤリと笑って半ば脅迫じみた言葉で迫る。
「好きに取っていいっつったのはてめェだ。責任持って付き合え」
もとより抵抗する素振りすら見せなかったサンジは、ふっと笑って指先でゾロの頬をなぞる。
「どこまで?」
「さいごまで」
当然とばかりに言うと、サンジはやれやれとでも言いたげに肩をすくめたが、ゾロが目をそらさないのに気づいて、わかったよ、と頷く。
「いいぜ、付き合ってやるよ、さいごまで。なんたってお前、誕生日だからな」
恋だの愛だの、ケーキみたいに甘ったるい言葉がなくてもそれだけ聞ければ充分だ。
ゾロは満足げに頷くと、さっそく待ちに待ったプレゼントの包装を開くことに集中するのだった。
リリース日:2016/11/12